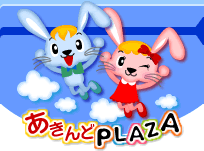 |
|
「あきんどPLAZA」の事務局です。今年度第7号のメルマガです。
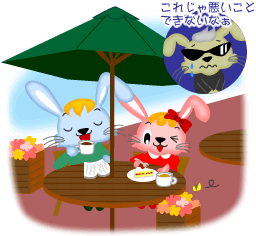
さて、前号でもお伝えしましたが10月に入り、各地の商店街で様々な取組みが行われています。テーマごとに見てみます。
まずは「防犯」。東京の新宿駅前商店街ではモア4番街通りをオープンカフェに変身させ、「危険で汚い街」のイメージを刷新する社会実験が始まりました。高知県の帯屋町商店街では18日に暴力団追放パレードが行われました。また、奈良市富雄地区では幼稚園児を対象にした防犯教室と110円で商品を販売する「110番セール」が14日に実施されました。
次は「空き店舗活用」。福岡市博多区の「みのしま商店街」では社会実験「おそとに出ようプロジェクト」が14日から始まり、商店街へ縁台を設置したり空き店舗に住民がカフェを開業しました。京都市北区の「御薗橋801商店街」では、1日500円、1週間までという破格の条件で空き店舗を貸し出す「夢のチャレンジショップ事業」が始まっています。また、鳥取県米子市の東倉吉町の「笑い通り商店街」にあった空き店舗「田園」を、障がい者介護施設兼障がい者の働く喫茶店に変貌させた社会福祉法人をモデルに、商業と福祉の連携で空洞化する商店街再生を考える「米子まちなおしフォーラム」が22~23日に開催されました。
そのほかにも、滋賀県彦根市の「河原の花しょうぶ通り商店街」の江戸時代の寺子屋を改装した市民交流施設、岩手県花巻市の中心商店街に試験的に導入された「足湯」などバラエティに富んでいます。
こうして見ると、切り口はそれぞれ地域の事情によって違いますが、商店街が地域のコミュニティの核になろうとする取組みが盛んになってきたと感じられます。
さて、前置きが長くなりました。それでは今回は以下のメニューでお届けいたします。
今回から、「欧米のまちづくり施策から示唆されること」と題してヨーロッパや北米のまちづくり施策を概観し、日本との違いなどを考察してみます。ご執筆は千葉大学助教授の村木先生です。
また、このメルマガへのご意見・ご感想も下さいね。
|
||||||||||
 |
|
||
諸外国のまちづくりに学ぶキーポイント
中心市街地の衰退や活性化の必要性という言葉が聞かれるようになって随分の時間が経過した。「自分の街は活性化した」「元気だから何も問題がない」といえるところは限られているものの、多くの都市が活性化に向けた様々な努力をしている。欧米の中心市街地でどこでも核となるのは、商業であり、賑わいの創出が結果として商業の活性化、つまり、大きな「稼ぎ」につながっている。ここでは、諸外国のまちづくりが、どのように進められているのか、キーポイントをまとめて説明したい。
■健康度調査
| 個別の商店では、売り上げの前月比、前年比などによりその状況を把握されると思われるが、まちづくりでの問題点は、こうしたまち全体の状況を把握するデータが確保しづらいということがある。それは所有形態が様々であり、一元的にデータを管理することが難しいためにある。では、欧米の都市ではこれはどのように行われているのだろうか。 イギリスの中心市街地活性化はタウンセンター・マネージメント(TCM)により、行われている。TCM活動で最初に行われるのは、まちの状況把握を行うことであり、それはヘルス・チェック、つまりまちの健康診断で説明されている。この調査は、採ることのできるデータを毎月、四半期、半年、1年ごとに確保し、そこからまちの状況を分析している。用いられるデータは、表に示した通りである。その内容は、大きくは、都市圏としての健康度(人口、雇用、産業構造)、中心市街地の健康度(空き店舗、小売りの売上高)、中心市街地の進展(来街人、駐車場、公共交通、犯罪、公共施設、道路清掃、施設、TCM活動)、その他の指標(観光、イブニング・エコノミー)といった指標による。これらはあくまでも指標例であり、都市により最も適したデータを用いることが、TCMの全国組織から指導されている。こうしたデータは、(1)活動資金を拠出する理事への報告、(2)一般市民への報告で使われている。それは、TCMの活動がいかに中心市街地の活性化に役立つかを示すには、こうしたデータの持つ意味が大きいからである。 では、こうしたイギリスの指標が、我が国の中心市街地で利用可能なのだろうか。売り上げ等の個店情報といった入手困難な情報も存在するが、多くの指標は、国勢調査、商業統計調査等の既存データを用いて分析可能であり、我が国においても十分入手可能な指標であるといえる。反対に、我が国ではほとんど設置されていない防犯カメラの設置がイギリスでは必要性の高い指標になっている点は興味深い。 |
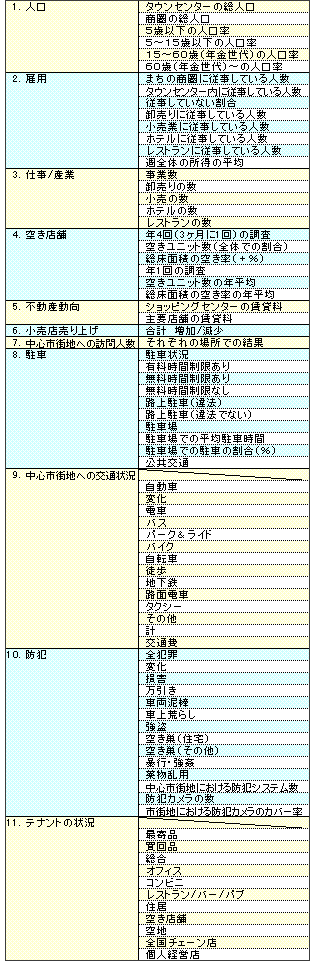 |
■Plan-Do-Check-Actionサイクル
イギリスでは、まちの現状を認識した上で、長所、短所を確認し、その上で計画づくりが行われている。長所を伸ばし、短所を克服するにはどうするのか、そのためのアクションプランと実施計画の立案が行われている。そして事業実施後、その評価が重視されている。このプロセスは、Plan-Do-Check-Actionと同じプロセスである。
| これは、事業実施の効果が得られれば、より多くの参画・投資が可能になるからであり、中心市街地での事業実施上の応援団確保には、現状把握とシビアな評価が重要になってくるからである。 投資の見返りは何か、投資分の効果がいかに図れるのか?中心市街地活性化の考え方は、商人の考え方ときわめて似ているのではないだろうか。活性化への参画・投資が、自分の売り上げに跳ね返ってくる-この論理の上に欧米の中心市街地のまちづくりは成り立っているといえるだろう。 |
 |
 |
|
||
POPで個性を伝える!
■商品には一つひとつ表示をつける
「この店は元気が無いなあ」と感じられるお店には共通点があります。接客に消極的であること、売場が清潔でないこと、さらには、陳列されている商品そのものの“自己紹介”が不十分なことです。商品にプライスカードがついていなかったり、ついていても書いてある内容やデザインにばらつきがあって読みにくい場合があります。
お客様一人ひとりに接客販売できれば良いのですが、小売店はそうもいきません。まずは、接客しなくても商品の基本情報がお客様にわかるよう、商品ひとつひとつにわかりやすい表示をつけておきましょう。
商品(ブランド)名と価格は、最低限必要な項目です。
■表示のきめごと
決められた事柄はきちんと表示しましょう。たとえば、生鮮食品の表示事項は次のように定められています。
| 農 産 物 | 名称、原産地 |
| 水 産 物 | 名称、原産地、解凍、養殖 |
| 畜 産 物 | 名称、原産地 |
| 玄米および 精米の表示概要 |
名称、原料玄米、内容量、精米年月日、 販売業者等の氏名または名称、住所及び電話番号 |
現在、消費税を含めた総額表示となっていますが、商店街のお店でたまにわかりにくい表示を見かけます。たとえば、ある日用雑貨店では、店頭のサンダルに「700円 税込735円」と同じ文字の大きさで併記されています。支払総額が末尾に書いてあるので誤認しやすく、文字数が多いので見た目がスッキリしません。まずは総額を表示し、本体価格や消費税を補足する、という表示が望ましいでしょう。
■POPはお店のセールスマン
商品には、それぞれオススメしたい「長所」「特徴」があります。たとえば「地物の原料を使っていて味が良い」「オーダーを受けてから作るのでお客様にぴったりのものができる」「輸入品と異なり数十年に渡って使える」などです。
| <商品の長所・特徴> 季節感…旬、はしり、流行、話題 安 さ…割安、ボリュームがある、おまけがついている 高品質…品質が良い、産地限定、手作り、耐久性が高い 早 さ…すぐできる、手軽に使える、簡単、手がかからない 限 定…先着、早い者勝ち、今だけ |
このような商品特徴は、お客様が商品を選ぶ際にもたいへん参考になります。文章やイラストでこれらをわかりやすく書いてあるものを「POP(購買時点の広告)」といい、ショーカード、プライスカード、その他商品情報を魅力的に伝えるものすべてをさします。
これらは、売場で、商品の良さを伝えてくれるものです。いわば「紙のセールスマン」。商品名、価格、原産地だけでなく、お店からのオススメの言葉をそのまま書いてお客様に商品の良さをアピールしましょう。
■お店とPOPで個性を伝える
神奈川県平塚市にある3p.m.(さんじ)は、ヘルシーフードを提案しているお店です。安心な食材を使い、目で見ても楽しい、というのが特徴。ユニークなお菓子やお惣菜の販売、デリバリー、オリジナルギフト、ケータリングサービス、ショップコーディネイト(レシピの提案)などを展開しています。ほっと落ち着く店内で、お菓子やカラフルなドリンクを楽しむこともできます。
こちらでは、商品一つひとつに丁寧な説明書きがつけられています。どれも内容が具体的で、見た目も統一されていて、つい読みたくなってしまいます。
たとえば「ポパイのほうれん草ケーキ 350円」には「ポパイでおなじみのほうれん草にはビタミンAがたくさん含まれています。つかれやすい人、鼻や喉の粘膜がよわく、かぜをひきやすい人などはビタミンAたっぷりのほうれん草が有効です」などと書かれていて「私、最近つかれ気味なのよね……」というお客様の購買意欲をそそります。
| また、全国からもオーダーが来る人気のおやつ「PPおやつボール」には、カラフルなスタンドPOPもついていて、商品とお店の統一感が感じられます。 このお店は、商品の質に加えて、お店とPOPで「キレイ」「センス」「楽しさ」を素敵にアピールしていて、スタッフのバランス感覚の高さがうかがえます。 3p.m.(さんじ) 代表 横田美宝子 神奈川県平塚市袖が浜17-61 |
 |
|
産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会商業部会合同会議の中間取りまとめ(案)は、「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを目指して」と題し、様々な都市機能の市街地集約(まちのコンパクト化)と中心市街地のコミュニティとしての魅力向上(中心市街地のにぎわい回復)を車の両輪として展開することが必要と提言しています。
行政とTMOが一体となり、中心市街地への居住回復と魅力向上に成果をあげ、コンパクトシティに向けて取り組んでいる長野県飯田市を紹介します。
■南信州の中心都市 飯田
| 長野県南端の飯田市は人口約10万人、天竜川が流れる伊那谷の中心に位置し、南信州地域の交通、文化、経済の中心都市です。しかし他の地域と同様に、モータリゼーションの進展、大型商業施設の郊外出店、郊外の宅地開発、高齢化の影響等も重なり、まちなかの居住人口は減少し中心市街地の魅力は半減してしまいました。 |  |
■再開発ビル「トップヒルズ本町」
こうした中、市街地の居住機能、コミュニティ機能、商業機能再生の核として、りんご並木に隣接した区域に住宅を中心とした再開発事業が計画され、平成13年7月に複合ビル「トップヒルズ本町」が完成しました。
 |
総事業費は約33億円、商業機能、交流・文化機能、住宅機能を併せ持つ地上10階で、駐車場(121台)が隣接し、1階には地元資本のスーパーマーケット、花屋、レストラン、雑貨店などがあり、2・3階は歯科医院、市役所の総合窓口、会議室、市民サロン、4階から10階は42戸の住宅で構成されています。施設は権利者11名による再開発組合が建設し、主な保留床の取得は、地元経済界、市民有志、市が出資した(株)飯田まちづくりカンパニー(TMO)が行いました。TMOが住宅分譲や店舗の賃貸などの不動産関連業務も行い、建物の管理も管理組合から受託しています。分譲住宅は即完売。この成功を受けて民間企業もマンションを建設するなど、周りへの波及効果も現れています。 |
■今後のさらなる施策
平成18年夏には、隣接地区に地元金融機関、人形美術館、商業、業務、住宅機能をもった複合ビルが完成予定のほか、平成19年に「健康維持・健康サポート・ケア付きコミュニティ住宅」機能を併せ持つ複合商業ビルの建設も予定されています。
■TMOの多彩な取り組み
| 160年前に建てられた商家の土蔵群を市が取得改修し、レストラン、市民ギャラリー等として再生された「りんご並木の三連蔵」の管理運営をTMOが行い、市民グループの拠点としてイベント開催(文化発信基地)など市民の憩いの場としてまちの魅力向上に役立っています。その他、空き店舗活用テナントビル、ケア付き高齢者共同住宅施設の建設、市民団体やNPOの活動支援等、趣向を凝らした様々な事業を行っています。 今後も行政とTMOが一体となったまちづくりの取り組みが進み、全国のモデル地域となることを期待しています。 |
 |
|
| このメールマガジンの発行は全国商店街振興組合連合会(平成17年度中小企業庁委託調査事業)により実施するものです。このメールはメールマガジンに登録いただいた方、インターネット上にホームページを公開している商店街の方々に配信させていただいております。
◆メールマガジン配信解除・配信先の変更 http://www.akindoplaza.com/change.aspx
◆ご意見・ご感想 info_master@akindoplaza.com
◆このメールに関するお問い合わせ info_master@akindoplaza.com
【発行日】2005年10月25日
【発行】全国商店街振興組合連合会 企画支援部
Copyright(C)2003-2005 あきんどPLAZA All Rights Reserved.
|

 メルマガアンケート実施中!
メルマガアンケート実施中!