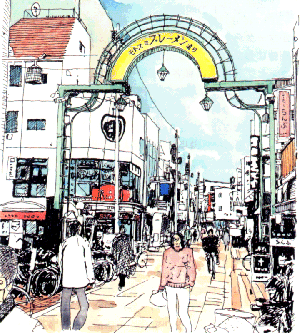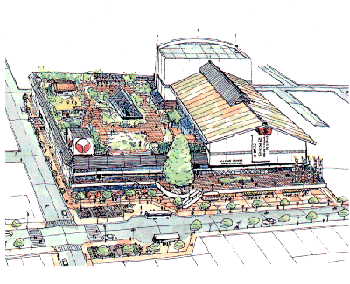| |
| 4.商店街マネジメントのリーダーシップ |
| (1)商店街のリーダーに求められるもの |
商店街のリーダーに求められるものとして、社会の動き、生活者の動きを見通す「洞察力」が大切です。また、会員・組合員からの「信頼性」、迷わずに決断し行動を起こす「行動力」、はリーダーとして不可欠なものとなります。
リーダーとしての「責任」とともに、他の役員や若手に対して権限を委譲し、責任は自らが負うという姿勢や「包容力」も必要です。
|
| |
| (2)リーダーの育成 |
| |
① リーダーの素質のある人の芽を摘まない |
やる気を出して何かをしようとしても周辺の人に足を引っ張られて何もできず、そのうち年を重ねてその素質の芽もしぼんでしまいます。
|
| ② 素質のある若者を育てる |
| 会社や他の法人組織と違って商店街では、次代のリーダーをかなり意識して育てないとリーダーは育ちません。 |
| ③ 女性リーダーヘの期待 |
|
お客がよくわかる女性の感性で商店街の運営や活性化に取り組むことも重要です。
|
| |
| (3)責任と権限 |
| |
① リーダーの権隈 |
| |
あくまでも権限は組合員から任されて行使するに過ぎません。そうした限界の中で組合員、会員に納得してもらえるかたちでの権限の行使ということになります。
権限を自分ひとりに集中させるのではなく、できるだけ理事、部会の長などのサブ・リーダーに委譲することが望まれます。
|
| |
② サブ・リーダーヘの権限の委譲 |
| |
サブ・リーダーに権限は委譲する、しかし責任はリーダーが負うという姿勢が望ましいと考えられます。
|
| |
③ 責任はリーダーが負う |
| |
サブ・リーダーに権限は委譲する、しかし責任はリーダーが負うという姿勢が望ましいと考えられます。
|
| |
④ 経済的責任の範囲を制限する方向 |
| |
法人組織の商店街の場合、理事長や理事の経済的責任の範囲を制限する方向を検討することが望まれます。
各事業に相互関連性が薄く、商店街が実施する事業は単独個別に実施されています。
|
| |
| 5.商店街マネジメントの財務 |
| |
① 商店街における財務の現状 |
| |
商店街の事業の内容は千差万別で、事業の規模は商店街により大きく異なります。また、事業の規模に応じて財務の内容にも大きな格差があり、商店街の持つ資産の状況もまちまちです。事業規模はあまり大さくないものの、長い間の蓄積により、また、投資事業の結果、比較的大きな資産を持つ商店街もあります。
|
| |
② 商店街における費用 |
| |
商店街における費用としては、商店街を維持するために経常的に必要ないわば「固定費」的費用と、商店街の活動を行うことにより発生する「変動費」的費用とがあります。
|
| |
③ 商店街の財源 |
| |
商店街の財源としては、組合員の賦課金(または会員の会費)、賛助組合員等(または賛助会員)の負担金や寄付金、国、都道府県、市町村や商工会議所、商工会などの機関からの補助金があり、その他、各種事業の実施に伴う事業収入があります。各種の事業のための財源は、事業参加者等の「受益者」が負担することを原則とすることが望まれます。
|
| |
④ 期待される商店街マネジメントの財務 |
| |
商店街におけるマネジメントとは、商業施設や商業基盤施設の整備を対象とした「デベロツプメント(まちづくり)業務」、各種の施設、設備、環境などに対する「メンテナンス(維持管理)業務」、経済等事業を中心として各種の分野での「ソフトマネジメント(経営営業管理)業務」に大別できます。商店街構成員(組合員他)の「企業店」、「生業店」、「副業店」など経営形態の分化や業種業態の多様化の傾向にあります。事業の目標、姿勢、営業方式などに大きな格差がある中で、商店街組織としてのすべてにおいて単純に一本化された運営は日増しに困難になりつつあります。このような中での商店街のマネジメントは、商店街全体として統一性を保ち各種の事業を行う一方、目標や意識が共通する商店群ごとに有志による任意のグループを組み、事業を進める「二重構造方式」がより有効であり、必要であると考えられます。"中心市街地活性化法"に沿って商店街においても、従来のように販売のための施設の整備や販売促進のための様々な活動を中心としたものだけではなく、社会的な役割を認識しつつ、各種のまちづくりを自らが積極的に進めたり、地域の諸活動に積極的に参加する事が求められています。
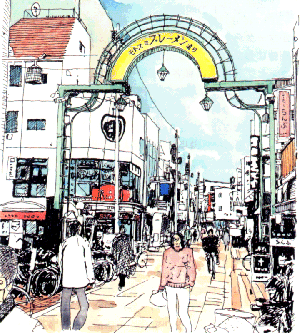
|
| |
| 6.商店街のマーケティング戦略. |
|
(1)マーケティングの必要性
|
余剰生産物が世の中にあふれている時代であり、消費者はもはやモノに辟易し、不要なモノはできるだけ排除しようとさえしています。
商店街にマーケティング的発想や仕組みが必要とされるのは、市場が成熟化し、加えて競合が激化している中で、いかにモノを販売するかという発想ではもはや立ち行かなくなっており、いかに需要を開拓するかについて真剣に考える時代になったということです。
|
|
| (2)商店街マーケティングのポイント |
| |
① 商店街コンセプトの明確化 |
| |
商店街がマーケティングを実践しようとする場合、まず、商店街のコンセプトを明確にしておくことが必要です。 商店街コンセプトとは、「顧客や市場や地域社会に対する商店街としての考え方」です。どのような理念や哲学で商店街を運営しようとしているのか、また、どのような特徴を持った商店街なのか、それを明確に表明したものが商店街コンセプトです。
コンセプトを前面に打ち出した商店街はまだ多くありません。しかし、今や多忙な消費者が増え、その上、多様な業態の小売業が増え、なおかつ、インターネットの普及があり、商店街は複雑な競合状況に置かれることになります。だからこそ、何をしてくれる商店街なのか、どのような特徴を持った商店街なのか、どのような発想で運営される商店街なのかが問われることになります。
|
| |
② 地域貫献の考え方 |
| |
商店街は地域密着型でなくてはなりません。商店街は単独で成り立っているわけではなく、地域からは有形・無形の資産の恩恵を受け、一方で地域にとって有形・無形の迷惑をかけながら商店街は生きているからです。
さらにこれからは少子・高齢化社会の到来が予定されており、地域に密着した商店街に対する期待は大きいと言えます。 |
| |
| (3)商店街らしいマーケティング戦略 |
| |
① 顧客獲得戦略 |
| |
顧客獲得戦略の基本は、「相手のことを知る」ということです。不特定多数の消費者を相手にするのではなく、地域の消費者を相手にするのですから、より具体的かつ個別に把握し、顧客のプロフィールを把握することが重要です。つまり、ナショナルチェーンにはできない、売り手と買い手との「顔のみえる関係」を作っておくことです。 |
| |
② 販売促進戦略 |
| |
販売促進の基本はコミュニケーションですから、各店舗での販売において人を通じてコミュニケーションを実現することが最も効果的といえます。 人的販売という方法で、商店街の魅力やイベント・サービスなどについての情報を伝達したり、逆に顧客からの情報をキャッチしたりできます。
|
| |
|
| |
③ 商品・サービス戦略 |
| |
商店街が行う商品・サービス戦略は、商店街のタイプやレベルによって異なります。マーケティング論で最も支持されているのは、消費者の持っている問題を解決する「便益の束」として商品をとらえる、メーカーが作った製品の分類で品揃えをするのではなく、消費者が持っている問題を解決するという視点で品揃えをすべきであるということです。
|
| |
④ 情報化戦略 |
| |
情報化戦略は、ポイントとなるのは、情報発信・受信・加工です。発信すべき情報があるのかどうか、受信できる能力を持っているのかどうか、蓄積したデータを加工して情報に仕立て上げる能力ガあるのかどうかです。
|
| |
⑤ 競争戦略 |
| |
新しい時代の商店街の競争戦略は、商店街としての独自性をどのように打ち出していくかを示すことです。商店街のコンセプトやアイデンティティーやセールスポイントを明確に打ち出すことで、自然と他の競合との差別化ができるし、消費者から見て商店街に行く理由も明快になります。
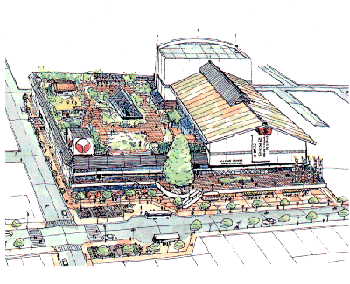
|